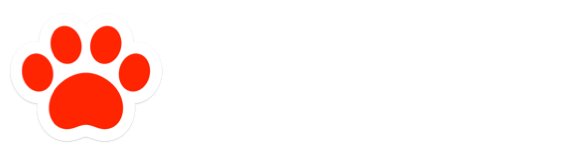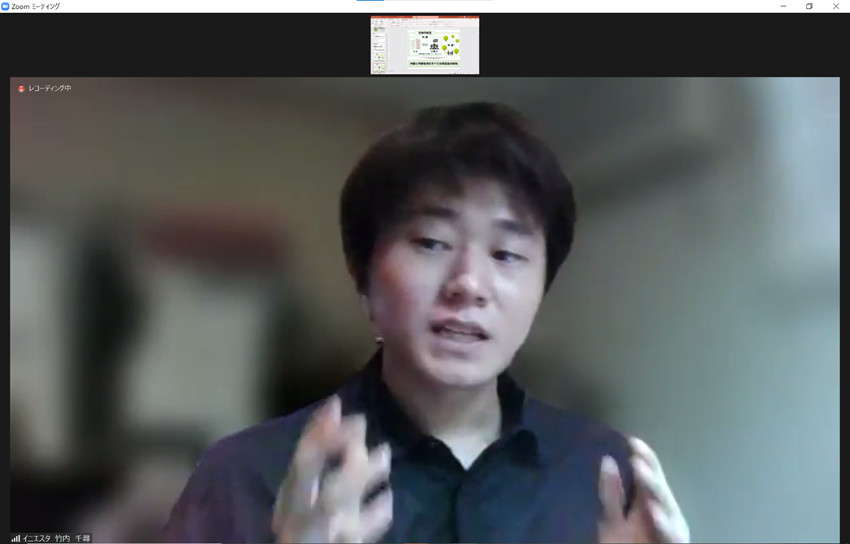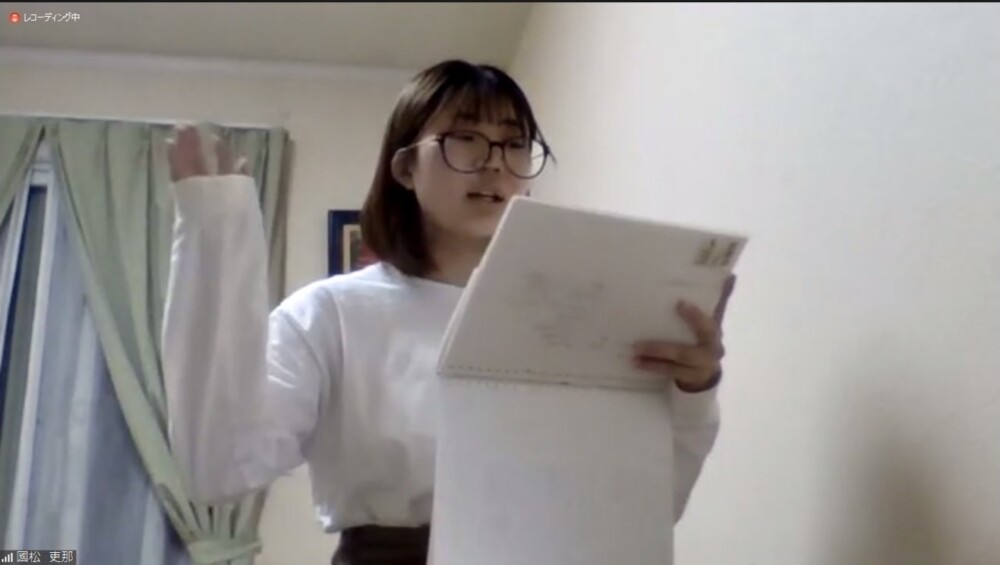ディベ王最終戦 2021年
9月18日にディベ王最終戦が行われました。
2年生にとっては、4年生の先輩方と関わる最後のディベ王。
2年生が中心となり今まで学んだことを生かした試合はどうなったのでしょうか。
【第一試合 ×14 vs〇Snow Zone】
「小売業の寡占化は社会的厚生を高めるのか」
是側 チーム14

<主張内容>
現在の小売業の特徴としては小売業が大規模少数になり交渉力がメーカーや卸よりも強くなっている。このことから情報・物流機能の高度化が進んできている。情報・物流機能の高度化が進んでいくことにより的確な品揃えができるようになったりワンストップショッピングを実現したりすることができ、消費者の満足度が上昇する。また在庫過多や機会ロスが減ることにより負の外部性が減っていく。これに加えて寡占化のデメリットである店頭価格の高止まりというものは小売業の寡占化という点では当てはまらないことが実地調査に行ってわかった。以上の二つから小売業の寡占化は社会的厚生を高めると主張する。
<感想>
今回のディベ王は最終戦ということもあり、2年生としては今まで学んできたことを全力で活用しようと意気込んでいました。しかし、今回の論題が今までとは違う理論系のお題となっておりとても難しい内容となっており、2年生だけで考えるのがとてもきつかったです。そのためディベ王の1・2回戦で先輩方のお力を貸していただいたこともあったので最終戦も先輩方のアドバイスに頼ろうとしてしまい、自分たちへの甘えが出てしまった部分がありました。しかし、後半になるにつれて2年生同士でも意見が出るようになり本番も勝つことができました。先輩方にはディベ王全体を通してとてもお世話になりました。ありがとうございました。(2年生)
今回のディベ王は最終戦ということもあり、2年生としては今まで学んできたことを全力で活用しようと意気込んでいました。しかし、今回の論題が今までとは違う理論系のお題となっておりとても難しい内容となっており、2年生だけで考えるのがとてもきつかったです。そのためディベ王の1・2回戦で先輩方のお力を貸していただいたこともあったので最終戦も先輩方のアドバイスに頼ろうとしてしまい、自分たちへの甘えが出てしまった部分がありました。しかし、後半になるにつれて2年生同士でも意見が出るようになり本番も勝つことができました。先輩方にはディベ王全体を通してとてもお世話になりました。ありがとうございました。(3年生)
否側 チームSnow Zone
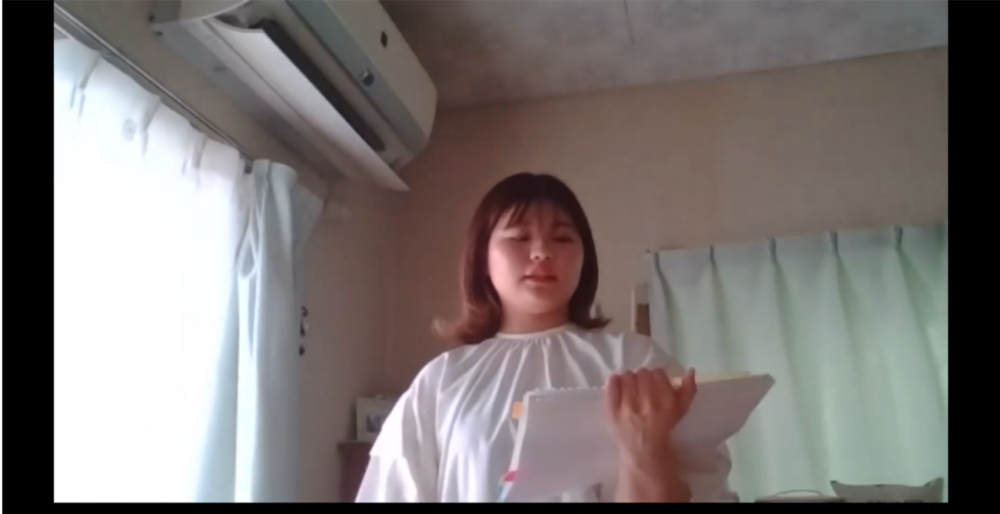
〈主張内容〉
小売業の寡占化が進むことで、価格が上がり消費者の負担が増える。また、消費者の選択肢の幅を狭め、消費者満足を下げるため、小売業の寡占化は社会的厚生を下げると主張しました。
差別化による費用増大で価格が上昇、高止まりし、オープン価格や価格の硬直性により消費者に負の影響を与えるため、消費者の負担が増える。
また、中小企業が大手に置き換わると、品揃えが標準化しニーズに応えられなくなる。
加えて、PB商品の増加により売り場が画一されるため、消費者の選択肢の幅を狭め消費者満足が下がるという主張を展開しました。
<感想>
ディベ王最終戦お疲れ様でした。今回は2年生が主体となって活動しました。
そのため、ストーリーの流れの理解ができ、本番では相手の穴と自分たちの主張を強めて言うことや、尋問を2年生主体で行うことができました。
反省点としては、その日の目標設定をせずに進めていたため、時間がかかってしまうことが多かったです。
本番では、分かりやすい尋問をすることができず、また、反駁では相手の立場に立った視点が取れませんでした。
そのため、準備段階ではスケジュール管理をしっかりと行うことを意識し、本番では全体の流れを意識した尋問を心がけ、フロアに分かりやすい反駁をするように努めて行きたいです。
約4カ月間ありがとうございました。(2年生)
ディベ王最終戦お疲れ様でした。
最終戦はオンラインでの開催となってしまい、非常に難しく大変だったと思います。
最後まで走り抜くことができたのは2年生が一生懸命に取り組んでくれたおかげだと感じています。
試合を重ねるごとに成長していく姿に、刺激をもらいました。
これからは先輩なしの活動が多くなると思いますが、今回のディベ王での経験を活かして頑張ってください。
長いようで短かった4ヶ月間、お疲れ様でした。(3年生)
【第二試合 〇イニエスタvs×エリンギの丘 】
「論題2 企業が上澄み吸収価格設定を継続して実施することは社会的厚生を高めるのか」
是側 チームイニエスタ

<主張内容>
上澄み吸収価格設定によって社会的厚生は高められる。現在、消費者はものを買う時に二極化していく現状にある。そのため、上澄み吸収価格設定を継続して行なっても商品が買われ、上澄み吸収価格設定のメリットである資金が集まりやすくなり、商品全体の質が向上し、さまざまな価格弾力性の消費者満足度が上昇する。また、上澄み吸収価格設定を行う企業はブランドイメージを重視しているため、SDGsなどの環境問題を積極的に行うため、外部の消費者満足度までも満たすことができる。二つの理由から上澄み吸収価格設定を継続して行うことは社会的厚生を高めることが出来ると主張する。
<感想>
今回のディベ王は最終戦ということもあり、2年生としては今まで学んできたことを全力で活用しようと意気込んでいました。しかし、今回の論題が今までとは違う理論系のお題となっておりとても難しい内容となっており、2年生だけで考えるのがとてもきつかったです。そのためディベ王の1・2回戦で先輩方のお力を貸していただいたこともあったので最終戦も先輩方のアドバイスに頼ろうとしてしまい、自分たちへの甘えが出てしまった部分がありました。しかし、後半になるにつれて2年生同士でも意見が出るようになり本番も勝つことができました。先輩方にはディベ王全体を通してとてもお世話になりました。ありがとうございました。(2年生)
ディベ王最終戦お疲れ様でした。
先輩と関われる最後のディベ王で、理論系という難しいお題に加え、オンラインでのグループワークで非常に難しく大変だったと思います。しかしその中でも2年生を中心にチームが一丸となり、総合優勝を掴むことができて本当に嬉しく思います。
3回の試合を通して2年生が日々成長していく姿を見て3年生としてはすごく嬉しかったです。
これからは対外試合やプレゼンコンテストなど2年生のみで大きな壁を乗り越えていく場面が多くあると思いますが、ディベ王での経験を糧に次に繋げて欲しいです!約4ヶ月本当にお疲れ様でした。(3年生)
否側 チームえりんぎの丘

<主張内容>
私たちは企業が上積み吸収価格設定を継続して実施することは社会的厚生を高めるかの否定側を担当しました。主張1では高価格で買うことに消費者が価値を感じなくなってきており上澄み吸収価格設定による満足度は減少していく話をしました。柱2ではこの戦略を行うことで企業は不当な利益を獲得し、消費者は搾取されているため社会を俯瞰した視点で観察した時に、消費者全体の満足度は下がってしまう。また、企業は今後それを加速させていくため消費者満足度はさらに下がっていくと考えました。以上のことから上澄み吸収価格設定を継続して行うことは社会的厚生を下げると主張しました。
<感想>
ディベ王最終戦お疲れ様でした。
準備段階では2年が主体となって話し合いを進めることができたため、前回までより内容の理解を深めることができ、ノートの取り方を見直すことで、情報共有や意見交換のしやすいように準備ができました。本番でも、理解の深まりとノートの取り方によって相手の主張を把握できるようになり、尋問内容も考えられるようになりました。反省点は、反駁時に相手の主張を汲み取った返しができず、言いたいことが伝わらなかった点です。試合では残念な結果となってしまいましたが、新たな課題を得ることができました。
ここまでご指導頂いたチームの先輩方、本当にありがとうございました。(2年生)
ディベ王最終戦、お疲れ様でした。
今回のディベートは、成長した部分と次への課題が見つかった良い機会だったのかなと感じています。
特に2年生は、今までのディベートで難しかった部分を反省し、最終戦で活かしたいという気持ちが強く伝わってきましたし、実際に活かせていました。
最終戦で課題が見つかり悔しい思いもあると思いますが、前の課題を克服したからこそ見つかったのだと前向きに捉えて、次の成長に繋げていってほしいです。
個人的には、「正しく伝える」難しさを感じる部分も多くありましたが、チームの雰囲気が悪くなることなく活発な議論を行うことができ、グループワークの楽しさを改めて感じました。
3回戦を一緒に走り抜けてくれたチームの皆、このような場を提供してくださった先生に深く感謝申し上げます。(4年生)
3回戦は、2年生を中心としてディベ王に取り組ませていただきました。
先輩方のアドバイスの集大成として自分たちが持てる力を発揮できたと思います。
2年生を支えてくださった先輩方本当にありがとうございました。
そしてディベ王最終戦お疲れさまでした。
(2年 竹内)